多くの企業では「部下育成」が課長職に課される重要な役割のひとつとされています。しかし、現場の声としてよく聞かれるのが「時間がなくて育成にまで手が回らない」という嘆きです。制度として研修や評価制度は整っていても、実際の現場では部下育成が実践されないケースが目立ちます。本記事では、その理由と解決のヒントを掘り下げていきます。
課長は現場の最前線でチームを率いる役割を担います。そのため、部下の指導や育成に加えて、自身の業務、上層部への報告、他部署との調整など多岐にわたる仕事を抱えています。業務過多の状態に置かれているため、どうしても部下育成の優先度が下がりがちになるのです。
さらに、育成は短期的に成果が見えにくく、数値目標に直結しないことから、他の緊急案件に押し出されてしまう傾向があります。
多くの職場では「売上や納期の達成」といった即効性のある業務成果が最優先とされます。すると、長期的な投資である育成はどうしても後回しにされがちです。
結果として、部下は成長機会を失い、いつまでも上司に依存する体質が生まれます。中長期的に見ると、課長自身の負担は減らず、組織としての生産性も停滞するリスクが高まります。
部下育成が後回しにされる大きな理由は「時間がない」という思い込みです。しかし、育成は別枠で時間を確保するものではなく、日常業務の中で自然に組み込むべきものです。
例えば、日々の業務指示を単なる依頼で終わらせず、考え方や判断基準を伝えるだけでも育成になります。育成を特別なタスクではなく「日常業務の延長」として捉えることで、継続的に取り組むことが可能になります。
まとまった時間を取るのが難しい場合でも、10〜15分の短い1on1を定期的に行うだけで効果は大きいです。ポイントは、業務の進捗確認ではなく、部下の思考や感情に焦点を当てることです。
「最近困っていることは?」「次に挑戦したいことは?」といった質問を投げかけることで、部下は自分の考えを整理しやすくなり、主体的な行動につながります。
わざわざ特別な育成時間を設けなくても、日常業務の中で育成のチャンスは数多く存在します。例えば、顧客対応や資料作成の場面で、課長が自ら手本を示し、次回は部下に任せるという流れを作ることができます。
このように実務と学びを一体化させる「ながら育成」は、業務負担を増やさずに育成効果を高める現実的な方法です。
部下が常に答えを求めてくる状況では、課長の負担は減りません。そこで重要なのは、答えをすぐに与えるのではなく、「あなたはどう考える?」と問いかける習慣を持つことです。
部下自身が考える機会を増やすことで、自立心が芽生え、課長の業務も軽減されます。最初は時間がかかりますが、中長期的には大きな成果につながります。
課長が業務に追われる大きな理由は、すべてのタスクを同じ優先度で抱え込んでしまうことにあります。まずは業務の棚卸しを行い、優先順位を明確にすることが必要です。
そのうえで、育成を「重要だけれど緊急ではない業務」として位置付け、意識的に時間を確保することが求められます。
課長がすべてを抱え込んでいては、育成の時間は生まれません。意図的に部下に業務を任せることで、自らの負担を軽減できます。その際は、権限を一度に丸ごと渡すのではなく、段階的に任せていくことがポイントです。
任せられた部下は責任感を持って取り組むようになり、自然と成長の機会が増えていきます。
部下育成を課長個人の努力に任せていては限界があります。人事部門は研修や仕組みを整備し、経営層は育成の重要性をメッセージとして発信するなど、組織全体で支える姿勢が不可欠です。
これにより、課長は安心して育成に時間を割けるようになります。
部下育成は「重要だ」と口では言っても、実際の評価制度に反映されていなければ形だけの取り組みになりがちです。多くの課長が「育成に時間を割いても評価されない」という不満を抱えるのはそのためです。評価項目の中に部下育成を正式に組み込むことで、課長は自分の業務の一部として育成を位置付けやすくなります。
例えば「部下のスキル向上度合い」「後任候補の育成状況」「チーム全体のパフォーマンス改善」など、育成の成果が数値や事実で評価される形にすることが望ましいです。こうすることで、課長は育成を後回しにせず、日常業務と同じくらいの優先度で取り組むようになります。結果として、育成の実践が組織文化に根付いていくのです。
育成が続かない理由のひとつは、取り組みの成果が見えにくいことにあります。成果が見えなければ、課長も部下も「やっても意味がない」と感じ、次第に形骸化してしまいます。そこで有効なのが、部下育成に関するKPI(重要業績評価指標)を設定することです。
KPIは「部下との1on1実施回数」「研修や学習機会の提供回数」「部下の業務改善提案数」など、具体的で計測可能な指標にすると効果的です。これにより、課長は「自分がやっていることが数字で見える」という実感を得やすくなりますし、部下も「自分の成長が組織に認められている」と感じやすくなります。
さらに、KPIを定期的に振り返ることで、取り組みの改善点を発見できます。単なる義務ではなく、成果を確認しながら次のステップに進める仕組みが、部下育成の定着を後押しします。
自社だけで部下育成の仕組みを構築しようとすると、発想が狭まりやすく、時間もかかってしまいます。その点、他社の取り組みを参考にすれば、既に効果が実証されている仕組みや工夫を効率的に取り入れることができます。
例えば「1on1を定期的に行う仕組み」「部下育成を評価制度に組み込む仕組み」「社内で育成の成果を共有する仕組み」などは、多くの企業が実施して成果を上げている代表的な施策です。これらは業種や規模を問わず応用できるため、導入のハードルも低いと言えます。
大切なのは、自社の課題や文化に合う形にアレンジすることです。単に真似をするのではなく、他社の知見を参考にしながら自社流にカスタマイズする姿勢が、効果的な育成制度を根付かせるための鍵となります。
課長にとって部下育成は重要な役割であるにもかかわらず、業務過多によって実践されない状況が広く見られます。しかし、日常業務に育成を組み込み、短時間の1on1やながら育成を活用すれば、限られた時間でも効果的に取り組むことができます。
また、タスクの棚卸しや権限移譲を通じて課長の負担を減らし、組織全体で育成を支える仕組みを整えることで、部下育成は定着していきます。評価制度やKPIを導入し、成功事例を共有することも継続的な改善に役立ちます。
部下育成を特別な活動ではなく「日常業務の一部」として位置付けることが、課長自身の負担軽減と組織力強化の両立につながるのです。
より確実に成果を出すためには、専門家の伴走を得るのも有効です。ページ下部で紹介しているビジネスコーチング会社3選には、組織変革や次世代リーダー育成を支援する企業が掲載されています。ぜひチェックして、最適なパートナーを見つけてください。
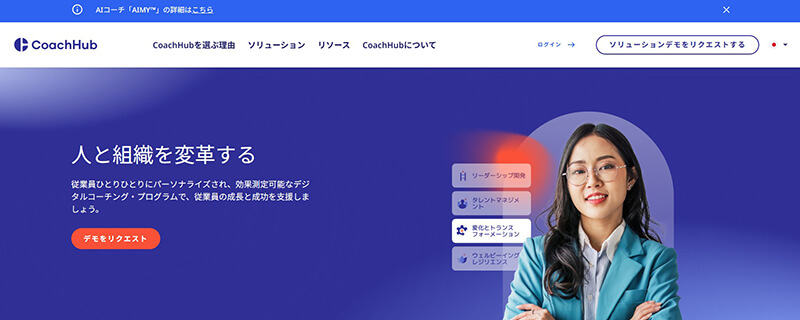
傾聴力・共感力・リーダーシップ力
行動科学・心理学に基づいたアプローチで、企業の管理職やチームリーダーが自身の行動や思考を深く見つめ直すプログラムを展開。
傾聴力・共感力・リーダーシップ力などが育つことで、社員の心理的安全性を高め、チームのエンゲージメントが向上します。

フィードバック力・対話力
実務に即した1on1支援と360度フィードバックなどにより、プレイヤー型の管理職が「人を育てる」マネジメントへ意識を転換。
OKR設計やピアセッションを通じて、対話力やフィードバック力“育成に必要なスキル”を実践の中で磨きます。

自己認識力・ビジョン構築
エゴグラム・360度サーベイ・AI対話分析を活用した1on1で、自己認識力とビジョン構築力を強化。
「どう見られているか」「何を大切にしているか」を問い直し、自らビジョンを語り、導くリーダーへの意識変革を支援します。