こちらの記事では、「キャリアコーチング」について解説していきます。キャリアコーチングの概要や、組織が抱えることが多いキャリアに関する課題、キャリアコーチングを取り入れることによって期待できる効果などをまとめました。
「キャリアコーチング」とは、それぞれの社員が自身の強みや価値観について整理を行い、将来のキャリアを主体的に描くための支援を目的としたコーチング手法を指します。
専門的な知識と経験を持ったコーチとの対話により、対象者のキャリア形成や成長をサポートしていきます。また、キャリア選択に対する不安や迷いを解消することによって、自信を持って意思決定を行っていけるようになる、という点もポイントといえます。そのため、具体的な目標の設定・達成を目指したアクションプランの策定も支援します。
キャリアコーチングを行う際には、対象者の強みや価値観、スキルなどについて客観的な分析を行い、自己理解を深めていくことからスタートします。その上で将来のキャリアビジョンを明らかにし、そこにたどり着くための具体的な行動計画について考えていきます。
このキャリアコーチングは1回行って終わりではなく、通常は複数回にわたって行われます。「相談者が自ら答えを見つけるプロセス」が重視される点もキャリアコーチングの特徴といえます。
近年、自身の将来的なキャリアに関する不安を持っている若手社員や中堅社員が多くなっているとされています。スマートフォンやPCを日々使用していると、キャリアに関するさまざまな情報を得られます。例えば、周りの人のキャリア状況や転職に関する情報などを目にする中で、「自分はこのまま成長していけるのか」「この先もこの会社にいて良いのか」といったように、将来的なキャリアに関する不安を抱えてしまうことがあります。
さらに企業では、かつてのような年功序列や終身雇用が薄れてきていることなどもあり、従来のように将来のビジョンが描きにくい状況になっているともいわれています。このような背景から、日々の業務の中で将来のキャリア像を描くことが難しくなっているといえます。
日々忙しい業務に取り組む中で、自分自身の強みや価値観についてしっかりと整理できていない社員が多い点も、組織におけるキャリア課題のひとつとされています。
自身の強みや価値観の整理が十分にできていない場合、自己理解が浅いままの状態になってしまいます。このような状況が続くと、自分がどのようなキャリアを望んでいるのかを判断することが難しくなり、「自分は将来どうなりたいのか」がわからないまま働き続けることになります。さらに、今後のキャリアに関しても周りに求められるがまま意思決定をしてしまうことによって、結果的にモチベーションの低下を招いてしまう可能性も考えられます。
上記のように、社員が自身の強みや価値観について整理ができておらず、将来に対するビジョンが曖昧な状態になってしまっている場合には、「自身はどのように成長したいのか」「どのようなことにチャレンジしてみたいのか」といった意思決定が難しくなります。このような状態が続くと、自身にとって必要なスキルなどについても判断できず、結果的に本人の成長や活躍が停滞するといった状況に陥ってしまうことになります。
また、場合によっては自身がミスマッチを感じているものの具体的な行動ができなくなってしまうことから、将来的に離職・転職リスクが高まってしまうといった問題にも繋がりかねません。
キャリアコーチングを行う上では、まずコーチとの対話を重ねていくことによって、自身が持つ価値観や強みを客観的に把握していきます。対話の中では専門的な手法やツールを用いて潜在的な強みや適性について可視化を行って自己理解を深めていきますが、これまで自分では気づけなかった部分が明らかになるケースも多くあります。
キャリアコーチングによって自己理解を深められると、「自分が本当にやりたいこと」や「自分が大切にしたい価値観」がわかり、これらに沿ったキャリアの方向性を見つけられるため、場当たり的な選択ではなく、しっかりと納得した上での意思決定を行えるようになります。
キャリアコーチングでは短期的な支援を行うのではなく、中長期的な視点を持ってキャリア形成のサポートを行っていく点も特徴といえます。例えば「5年後はどうなっていたいのか」「10年後自分はどうなっていたいのか」という目標や、その目標を達成するにはどのような経験やスキルを積むべきなのかを洗い出した上で計画を作成するなど、中長期的な目線を大切にした支援を行っていきます。
ここで策定した計画に沿ったスキルアップなどを目指して行動することによって、キャリアプランに沿った具体的なアクションに繋げていけるようになります。
「自分の意思で選ぶ」という点がキャリア形成の鍵であることから、キャリアコーチングでは、社員が主体の意思決定を促すための支援を行っていきます。ここでのポイントは、意見を押し付けるのではなく、「選択肢を整理するサポートに徹する」という点です。
キャリアコーチングを通じて自身で課題や選択肢を考えることによって、決断する力が身につき、さらにその力を今後のキャリアに活かすことが可能に。結果として、自身が十分に納得した上でのキャリアプランの構築や意思決定を行えるようになっていきます。
キャリアコーチングを行うことによって、社員それぞれの自己効力感とモチベーションの向上が期待できます。
「自己効力感」とは、「目標を達成するための能力を自身が持っている」と認識することを指しています。簡単にいうと、「自分ならできる」「きっとうまくいく」と思える認知状態のことであり、「自分にはそれだけの能力がある」と信じられている状態である、という点がポイントです。
自己効力感が高まるとさまざまなことにポジティブな意志を持って取り組めるようになるため、日々の仕事に対するモチベーションが向上していきます。さらに、困難に直面した場面でも前向きに行動していくための力にもつながり、パフォーマンスにも良い影響を及ぼすことが期待できます。
キャリアアップを実現するには、具体的な目標を設定することが重要となってきます。キャリアコーチングでは、自分の現状について客観的に把握して自身が持つ強みや弱みを分析した上で、達成したい目標を具体的に設定しますが、ここでは目標を達成するために必要となる経験やスキルについても明らかにします。そして「短期」、「中期」、「長期」に分けた形で目標を設定し、それぞれの目標の達成に向けて行動計画を立てていくことになります。
このように、キャリアコーチングでは漠然とした目標設定にとどまらず、「いつまでに何をするか」といった具体的な行動計画を設計します。そして計画を立てて終わりではなく、進捗を定期的に確認していきますが、必要に応じて計画の修正を行うことも。このような取り組みの中で、自身で考えて行動に移す力や自身で立てた計画を実行していく力を強化することができます。
その場限りの自己分析で終わるのではなく、キャリア形成において長期的な視野で考えられるといった点も、キャリアコーチングの大きなメリットであるといえます。現在は多くの人が現時点での課題や悩みに対応するのに精一杯になっている状況であり、5年後や10年後のキャリアに対するビジョンを描けていない状況にあるといわれています。
キャリアコーチングでは、コーチと対話を行っていくことによって「数年後にはこのような経験を積んでみたい」「将来的にマネジメントに挑戦したい」といったように将来の自分像を具体的に描くことができ、さらにそこに至るまでの行動計画を設計できる点がポイントです。このように中長期的な行動計画を立てていくことで、キャリア選択の幅を広げることにも繋がります。
ビジネスコーチング以外の法人
向けの
コーチングの種類
について詳しく見る
こちらの記事では、「キャリアコーチング」の概要や期待できる効果などについて解説してきました。
キャリアコーチングとは、専門家との対話を行うことによって自己理解を深め、社員の主体的なキャリア形成に繋げていくためのプロセス。社員ひとりひとりの成長を促し、さらに組織全体の活力を高めるために有効なアプローチであるといえます。コーチの対話によって自己理解を深め、具体的な行動を促していくことによって、キャリアに関する迷いや不安を解消し、働く人の選択肢や可能性を広げることにつなげられます。
そして、社員が自らのキャリアと向き合えるキャリアコーチングは、それぞれの社員の成長を促進することができるため、結果的に企業の競争力の向上につながっていくと考えられます。このような面からも、キャリアコーチングは企業が人材の育成や定着について考える上で重要性を増しているといえるでしょう。
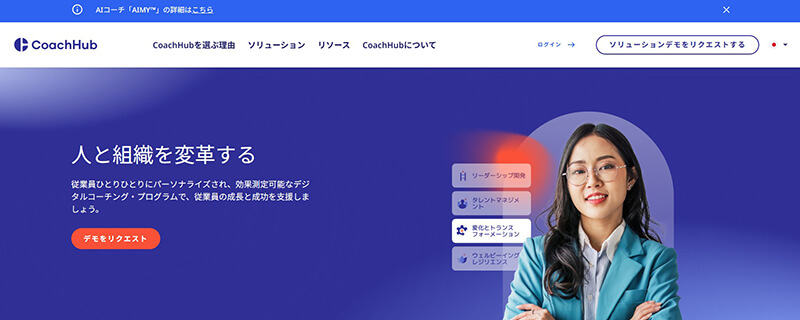
傾聴力・共感力・リーダーシップ力
行動科学・心理学に基づいたアプローチで、企業の管理職やチームリーダーが自身の行動や思考を深く見つめ直すプログラムを展開。
傾聴力・共感力・リーダーシップ力などが育つことで、社員の心理的安全性を高め、チームのエンゲージメントが向上します。

フィードバック力・対話力
実務に即した1on1支援と360度フィードバックなどにより、プレイヤー型の管理職が「人を育てる」マネジメントへ意識を転換。
OKR設計やピアセッションを通じて、対話力やフィードバック力“育成に必要なスキル”を実践の中で磨きます。

自己認識力・ビジョン構築
エゴグラム・360度サーベイ・AI対話分析を活用した1on1で、自己認識力とビジョン構築力を強化。
「どう見られているか」「何を大切にしているか」を問い直し、自らビジョンを語り、導くリーダーへの意識変革を支援します。