近年、若手社員の早期離職、特にその理由が見えにくいケースに頭を悩ませる企業が増えています。定期的な1on1や面談制度を設けても、社員の本音を引き出せず、育成の成果も不透明。「一体、何をすれば離職を防げるのか」「育成投資は本当に効果を上げているのか」といった問いは、多くの人事責任者が抱える切実な課題でしょう。
その解決策の一つとして注目されるのが「コーチング」です。しかし、多額の費用をかけて管理職向けのコーチング研修を導入したにもかかわらず、現場で一向に実践される気配がない、という声も少なくありません。
本記事では、なぜコーチング研修が「やりっぱなし」で終わってしまうのか、その理由を深掘りし、研修の学びを現場での実践、そして組織文化へと昇華させるための具体的な仕組みづくりとアプローチについて考察します。
管理職が研修で学んだコーチングを実践しない背景には、複合的な要因が存在します。
まず、研修内容そのものに課題があるケースです。講師から「リーダーシップを発揮しよう」と熱弁されても、内容が抽象的で理論に偏っていれば、管理職は具体的に何をどう行動すれば良いのか分からず、翌日からの実践には繋がりません。
また、管理職一人ひとりが抱える悩みやチームの状況は千差万別であるにもかかわらず、画一的な内容では受講者個別の課題が無視され、「自分には関係ない」と感じさせてしまいます。特定のメソッドを万能薬のように提示する研修も、かえって現場との乖離を生む原因となり得ます。
次に、組織的な問題です。例えば、トップダウンの文化が根強い組織で、研修でボトムアップ型のマネジメントを学んでも、管理職がそれを実践するのは極めて困難です。経営トップのスタイルや組織カルチャーとの不整合は、実践を阻む大きな壁となります。
そして、受講者である管理職自身の問題も見過ごせません。研修の目的や必要性を理解せず、会社命令で参加している「やらされ感」が強ければ、学習意欲は湧きません。インプット中心でアウトプットの機会が少ない研修では、知識は定着せず、ただ時間を浪費したという感覚だけが残ります。
そして決定的なのが、研修後の成果や効果を評価する仕組みの不足です。実践した結果、部下やチームにどのような変化があったのかを可視化し、振り返る機会がなければ、管理職自身もその有効性を実感できず、モチベーションは失われてしまいます。
コーチングは、一度の研修で習得できるほど単純なスキルではありません。人材育成における有名な法則に「70:20:10の法則(ロミンガーの法則)」がありますが、これは人の成長において、研修から得られる学びはわずか10%に過ぎないことを示唆しています。
多くの研修は、短期間に多くの情報を詰め込む形式になりがちです。そのため、受講者は新しい知識を十分に消化し、実践できるレベルに至る前に研修を終えてしまいます。結果として、情報量の多さに圧倒されたり、アウトプットの機会がないまま内容を忘れてしまったりするのです。
加えて、研修後のフォローアップや、実践を後押しする組織的なサポートがなければ、管理職は現場で「孤軍奮闘」せざるを得ません。学んだ通りに実践してもうまくいかない、という壁にぶつかった時、相談できる相手や仕組みがなければ、やがて実践を諦めてしまうのです。
このように、研修で学んだことと現場での実践との間に生じるギャップを放置することが、研修を「やりっぱなし」にしてしまう最大の要因と言えるでしょう。
管理職がコーチングの実践をためらう理由として、「日々の業務に追われ、そんな時間は取れない」という声も定番です。従来の指示命令型マネジメントに比べ、部下の話に耳を傾け、内省を促すコーチングは、時間がかかるように感じられても不思議ではありません。
この懸念を払拭するには、短時間でも効果的なコーチングが可能であることを具体的に示す必要があります。その有効な手法の一つが、**「GROWモデル」**のような対話のフレームワークです。
このモデルに沿って対話を進めることで、単なる雑談に終わらせず、部下の思考を整理し、自律的な行動を効率的に引き出すことができます。研修の場で、こうしたフレームワークを用いた実践的なケーススタディやワークショップを取り入れ、「これなら自分にもできそうだ」という成功体験を積んでもらうことが、現場での実践イメージを育む上で極めて重要です。
日常の何気ない一言や、週に一度の15分の面談が、部下の成長を促す大きな投資になり得ることを理解してもらうことが、この誤解を解く鍵となります。
研修で得た学びを一時的なもので終わらせず、現場での行動変容に繋げるには、研修後の継続的なフォローアップと、それを支える組織的な環境整備が不可欠です。学びが定着し、実践されるためには、「人を育てるリーダーとしてのマインドセット」と「学びを現場で活かす仕組み」の両輪が欠かせません。具体的なフォローアップ施策として、下記を検討してみてください。
研修で学んだフィードバックの手法を、実際の人事考課やキャリアプランニングとどう連携させるかなど、部署や職種の実態に即した行動定着の具体的な手法を組織として提示・支援します。
定期的な1on1ミーティングの場を制度として確保するだけでなく、管理職同士がコーチングの実践状況や悩みを共有できる勉強会などを設け、「一人で頑張る」のではなく「仲間と学び合う」文化を醸成することが、継続の力になります。
コーチングスキルの習得には時間がかかります。組織として短期的な成果ばかりを求めず、管理職の挑戦を温かく見守り、支援し続けるという明確なメッセージを発信することが、彼らの安心感とモチベーションに繋がります。
多忙な管理職がコーチングを実践するには、日常業務の中に自然に組み込める工夫が求められます。前述のGROWモデルなどを活用し、構造化された対話を意識することで、限られた時間内でも部下の自律的な行動を効果的に促すことが可能です。
その最適な実践の場が、週次などで行う1on1ミーティングです。重要なのは、その1on1の目的(例:信頼関係の構築、部下の成長支援、キャリアに関する対話など)を事前に明確にすることです。目的に応じた問いかけや傾聴のスキルを、研修の場でロールプレイングやケーススタディを通じて具体的に学ぶことで、管理職は「明日から使える」という実践的な手応えを得ることができます。
知識のインプットに終始するのではなく、こうした実践的な演習を通じて、日常のささいなコミュニケーションが、部下育成という投資を大きな成果に変えるか、あるいは損失にしてしまうかの分かれ目になるという意識を醸成することが重要です。
管理職のコーチング実践を促進し、組織に定着させる上で、その成果を人事評価に適切に反映させることは有力な動機づけとなります。これにより、管理職はコーチングへの取り組みが、自身の評価や組織目標の達成に直結する重要な業務であると認識するようになります。
MBO(目標管理制度)などの評価項目に、「部下育成への貢献」や「チーム内の心理的安全性の向上」といった、コーチングの実践度を測る指標を組み込みます。
MBO(目標管理制度)などの評価項目に、「部下育成への貢献」や「チーム内の心理的安全性の向上」といった、コーチングの実践度を測る指標を組み込みます。
また、研修後の変化を測定する仕組みを導入します。例えば、サーベイツールを用いて部下のエンゲージメントスコアや上司への信頼度の変化を定量的に測定したり、部下へのヒアリングを通じてコミュニケーションの質の変化を定性的に評価したりします。育成投資の効果を客観的なデータとして把握できるようにする点が大切です。
コーチングの実践度合いや、それによってもたらされた部下の成長、チームの成果などを、昇進・昇格や賞与などの処遇に連動させることで、管理職の努力が正当に報われる仕組みを構築します。
コーチングを一部の管理職のスキルセットで終わらせず、組織全体の文化として定着させるためには、経営層と人事部の強いコミットメントと戦略的なサポートが不可欠です。
なぜ今、自社にコーチングが必要なのか。コーチングは、自社のどのような経営課題を解決するためなのか。経営戦略と人材戦略を連動させることが、人的資本経営の要諦です。管理職研修を、この大きな戦略の一部として位置づける必要があります。
経営層自身が、研修費用を単なる「コスト」ではなく、組織の競争力や従業員エンゲージメントを高めるための未来への「投資」と捉えることが、全ての始まりです。この意識転換があって初めて、継続的な支援が可能になります。
管理職にコーチングの実践を求めるのであれば、経営トップ自らのマネジメントスタイルも変革していく必要があります。経営層の言動は、組織文化に最も大きな影響を与えます。
人事部は、研修を企画して終わりではなく、実践と定着までを視野に入れた継続的な支援体制を構築する役割を担います。管理職が安心して実践を続けられる環境や仕組みを整えることが、行動変容を確実なものにします。
管理職がコーチングを「やらされる」義務感から、「自らやりたい」と意欲的に取り組むように変わるためには、いくつかの工夫が必要です。
管理職自身が、コーチングを実践することで「部下が自律的に動き、結果的に自分の業務負担が減る」「チームの目標達成が容易になり、自身の評価も上がる」といった具体的なメリットを実感できることが、何よりの動機づけとなります。
コーチングの本質は、ティーチングのように「答えを与える」ことではなく、対話を通じて「相手が自ら答えを見つけるのを支援する」ことです。このスタンスが腹落ちすると、管理職は部下との関わり方を根本から変えることができます。ただし、状況によってはティーチングも必要であり、その使い分けを明確に伝えることも重要です。
抽象論ではなく、自社で実際に起こりうるようなケーススタディやシミュレーションを用いることで、コーチングの有効性を具体的に示します。また、ワークショップなどを通じて、部下の主体性が高まることで、管理職・部下・組織それぞれにどのような良い変化が生まれるかを自ら考えてもらうことも効果的です。
人は、具体的な成功事例や身近な手本を見ることで、「自分にもできるかもしれない」と行動を起こしやすくなります。
他社がコーチング導入によってどのように組織を変革し、ビジネス上の成果を上げたのか、具体的な事例を示すことも有効です。例えば、自律的な学習文化の醸成に成功した企業の事例や、管理職が自身の強みを発見し、部下への権限委譲を進めた事例などを共有することで、目指すべき姿が明確になります。
社内でコーチングを効果的に実践している管理職を「ロールモデル」として称賛し、その行動や思考プロセスを共有する場を設けます。彼らの生の声を聴くことは、他の管理職にとって何よりの刺激となり、実践への具体的なヒントを与えてくれます。
研修で学んだスキルを実践し、磨き上げるためには、管理職同士が互いにサポートし合う仕組みがある方が望ましいです。ペアを組んで互いにコーチングを行ったり、実践上の悩みをフィードバックし合ったりする制度の導入を検討しても良いでしょう。
研修で学んだ内容を実際の業務に即して議論し、学びを深めることができます。孤立せずにスキルを磨ける「相互学習の文化」は、継続のための強力なエンジンとなります。
行動変容を促すためには、定期的な振り返りが不可欠です。研修後に、設定した目標に対してどの程度実践できたか、どのような課題に直面したかを自己確認するセッションを設けます。自身の現在地を客観的に把握し、次の行動計画へと繋げることができます。また、現場で生じた課題を収集し、次回の研修内容を改善していく上でも、この振り返りのプロセスは欠かせません。
時には、内部の力だけでは限界がある場合もあります。特に、支援的なコミュニケーションに慣れていない管理職に対しては、外部のプロフェッショナルなコーチから「コーチングを受ける体験(関わられる体験)」をしてもらうことが、スキルの本質的な理解に繋がります。コーチングを通じて自身の課題や強みへの自己解像度を高める体験は、部下と関わる際の姿勢に大きな変化をもたらすでしょう。
管理職向けコーチング研修が本来の効果を発揮せず、現場で実践されない背景には、「やりっぱなし」の研修設計、組織文化との不整合、そして実践を評価・支援する仕組みの欠如といった根深い問題があります。研修で得た学びが管理職の行動変容に繋がらない限り、その投資は単なる「コスト」で終わってしまいます。
研修の成果を最大化し、コーチングを組織の力に変えるためには、スキル研修という「点」の施策ではなく、以下のような包括的な「線」と「面」でのアプローチが不可欠です。
適切なプログラム設計や組織を挙げた粘り強いサポートを作る点で悩みがあれば、ビジネスに強いコーチングのプロへ依頼するということも良い方法です。管理職もその部下も自立自走するためにどうするか、コーチングの定着化を自社にあった形で導入できる手助けをしてくれます。
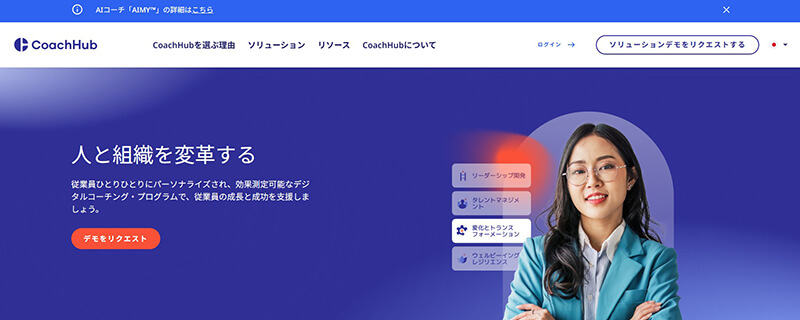
傾聴力・共感力・リーダーシップ力
行動科学・心理学に基づいたアプローチで、企業の管理職やチームリーダーが自身の行動や思考を深く見つめ直すプログラムを展開。
傾聴力・共感力・リーダーシップ力などが育つことで、社員の心理的安全性を高め、チームのエンゲージメントが向上します。

フィードバック力・対話力
実務に即した1on1支援と360度フィードバックなどにより、プレイヤー型の管理職が「人を育てる」マネジメントへ意識を転換。
OKR設計やピアセッションを通じて、対話力やフィードバック力“育成に必要なスキル”を実践の中で磨きます。

自己認識力・ビジョン構築
エゴグラム・360度サーベイ・AI対話分析を活用した1on1で、自己認識力とビジョン構築力を強化。
「どう見られているか」「何を大切にしているか」を問い直し、自らビジョンを語り、導くリーダーへの意識変革を支援します。