こちらの記事では、「フィードバックスキル向上プログラム」について紹介しています。組織が抱えるフィードバックに関する課題やフィードバックスキル向上プログラムの特徴、期待できる効果などをまとめています。より良いフィードバックを行い、部下や組織の成長に繋げたいと考えている方は、ぜひ参考にしてください。
チームや組織をまとめるマネージャーは、部下の成長を通じて成果を出していくことを求められます。その中では、日々部下に対してフィードバックを行い、部下の成長やモチベーションの維持に取り組んでいく必要があります。
しかし、「一方的なフィードバックになってしまう」「場当たり的な内容しか話せない」「フィードバックのやり方に自信がない」といったように、フィードバックについてさまざまな課題を抱えている組織もあります。
「フィードバックスキル向上プログラム」は、部下の成長を促すとともに信頼関係の強化を目的として、効果的な伝え方を学ぶプログラムです。これは、単に評価を行えるようになるだけではなく、対話を通じて部下の行動変容や成長を引き出すためのスキルを高める取り組みである点がポイントといえます。
フィードバックの内容が一方的になってしまう、場当たり的なものになってしまうといった場合には、十分な効果が得られなくなってしまいます。
例えば上司からの一方的なフィードバックが行われた場合、部下は「自分の意見を受け入れてもらえない」と感じてしまうため、フィードバックの内容を素直に受け入れにくくなります。そして、対話が行われないフィードバックの場合、正しくその意図が伝わりにくくなることから、誤解を生む可能性も考えられます。そして、本質的ではない場当たり的な内容のフィードバックでは、期待通りの効果を得ることが難しくなってしまいます。
フィードバックを行う側が、「どのように伝えたら良いかわからない」といった形で不安を感じているケースもあります。このような場合、フィードバックを受けた側も内容をうまく理解できず、行動改善に繋げることが難しくなる可能性が高いといえます。
さらに部下の行動改善が必要な場合などにも、結果的に伝えたい内容が伝わらなかった、意図がうまく伝わらず部下のモチベーションを下げてしまったというような状況に陥ってしまう可能性もあります。
フィードバックを行う場合には、部下の緊張をほぐして本音を引き出すことによって、より成長につながるアドバイスなどをしやすくなるといった面があります。しかし、上司と部下の間に信頼関係が築けていない場合や、心理的安全性に欠ける環境である場合には、効果的なフィードバックを行うことが難しくなります。
また、心理的安全性が高い環境の場合、部下は他者からのフィードバックを受け入れやすくなるといった面もあります。間違いや失敗をしてしまったとしてもそれを受け入れる姿勢を持つことができ、改善に向けたフィードバックを積極的に受け取り、成長に繋げられるといった状況が生まれます。
このような面から、フィードバックを行う際は、お互いの信頼関係を築いておくことや、心理的安全性の高い環境を構築しておくことが非常に重要であるといえます。
フィードバックのスキル向上を目的とした研修の特徴として、座学のみで学ぶのではなく、ロールプレイやケース演習なども含めた実践的な学習を行っていくという点が挙げられます。ロールプレイを行う場合には、より深く学べるように3人1組で進めていきます。
具体的な進め方としては、「フィードバックを行う人」「フィードバックを受ける人」「オブザーバ」という役割に分かれます。オブザーバという役割を設けることで、フィードバックの様子を客観的に確認できるようになる点がポイントです。例えば抽象的な表現があった場合などに指摘をするほか、フィードバックを行う時の姿勢や態度なども気づいた点があれば指摘をします。また、オブザーバ役の人も他の人がフィードバックを行っている様子を見られるため、さまざまなことを学べるというメリットもあります。
プログラムでは、「ポジティブな伝え方」を重視している点もポイントです。ポジティブなフィードバックを行うことには、「部下の成長のため」と「お互いにより良い関係性を築く」という2つの目的があります。
まず、部下に対してポジティブな内容のフィードバックを提供することにより、部下は自信をつけられるため、その後の行動もより良いものに変わっていくというメリットがあります。さらに、心理的安全性を高める効果も期待できます。心理的安全性が高い職場では、誰もが自分の意見や質問について不安を感じずに発言でき、失敗を恐れずに新しい挑戦ができます。このような環境であれば、活発な意見交換を行うことが可能になります。
その結果、お互いの信頼関係も強化できるため、改善点や課題を指摘するフィードバックも行いやすくなります。
画一的な内容を提供するのではなく、それぞれの組織の状況に応じてプログラムのカスタマイズを行うケースもあります。この場合、例えば「抽象的なフィードバックしかできない」「年上の部下に遠慮してフィードバックができない」など、それぞれの組織ではどのような点が課題となっているのかを確認した上で、プログラムの内容を決定していきます。座学やロールプレイを組み合わせる、集合研修と個別指導研修を使い分けるといったパターンなどが考えられます。
状況によりプログラム内容をカスタマイズが行える場合には、自社が必要とする部分に絞って学ぶことができるため、より効果的に必要なスキルを身につけることが可能となります。
フィードバックスキル向上プログラムで理解度を深めることによって、より効果的なフィードバックを行えるようになります。そうなると、部下の成長を促すことにつながっていきます。それぞれの部下の個性や強みなどに合ったフィードバックを行えるようになるため、主体性を育てられる点に加えて、相手の納得感を引き出しつつ客観的・具体的に指摘を行えるようになることから、行動改善につなげられるようになります。
上司のフィードバックに関するスキルが向上すると、1on1を行った場合などに部下と効果的な対話が行えるようになります。この場合、部下と上司の信頼関係が強化されることで、心理的安全性が高まっていきます。
心理的安全性が高い場合、不安を感じずに意見を述べられる環境であるため、活発な意見交換につながります。このような職場では新しい発想やアイデアが生まれやすく、さまざまな変化やトラブルなどにも迅速な対応が可能に。さらに業務の効率も向上するといった効果も期待できます。
エンゲージメントとは、深いつながりを持つ関係性を示す言葉です。さまざまな場面で用いられており、ビジネスにおいては「職場と従業員」や「企業と顧客」の関係性を指すことが一般的となっていますが、これは相互の信頼感や共感、持続的な関わりを基盤としています。
より良いフィードバックを行えると組織全体のエンゲージメントが向上し、健全なフィードバック文化の醸成につながっていきます。これは、「フィードバックは成長を支えるプロセスである」という認識を組織全体で持つことができるため。さらにメンバー同士のコミュニケーションも活発化し、組織全体の生産性向上にもつながっていくという効果も期待できます。
こちらの記事では、「フィードバックスキル向上プログラム」について解説しました。
フィードバックスキル向上プログラムは、成長支援を軸として、建設的な対話を実現していくための取り組み。一方的な評価を行うのではなく、上司と部下の間に構築された信頼関係に基づいた、双方向のフィードバックを促していく点が特徴といえます。効果的なフィードバックの提供は、部下の成長を促せるとともに信頼関係を強化できることから組織全体のエンゲージメント向上につながり、健全なコミュニケーション文化を根付かせる基盤となります。
より良いフィードバックを行うためのスキルを身につけ、部下や組織の成長に繋げたい、と考えている方は、ぜひこちらのプログラムに注目してみてはいかがでしょうか。
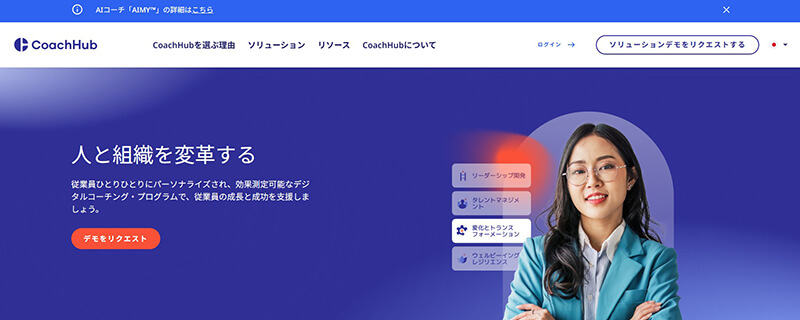
傾聴力・共感力・リーダーシップ力
行動科学・心理学に基づいたアプローチで、企業の管理職やチームリーダーが自身の行動や思考を深く見つめ直すプログラムを展開。
傾聴力・共感力・リーダーシップ力などが育つことで、社員の心理的安全性を高め、チームのエンゲージメントが向上します。

フィードバック力・対話力
実務に即した1on1支援と360度フィードバックなどにより、プレイヤー型の管理職が「人を育てる」マネジメントへ意識を転換。
OKR設計やピアセッションを通じて、対話力やフィードバック力“育成に必要なスキル”を実践の中で磨きます。

自己認識力・ビジョン構築
エゴグラム・360度サーベイ・AI対話分析を活用した1on1で、自己認識力とビジョン構築力を強化。
「どう見られているか」「何を大切にしているか」を問い直し、自らビジョンを語り、導くリーダーへの意識変革を支援します。