管理職候補はいるが、昇進への不安や辞退も多い──。多様な人材が活躍する今、女性管理職の育成は企業成長の鍵を握る重要施策です。
本ページでは、その意義や背景、具体的な育成手法について紹介します。
管理職候補の女性に向けて、リーダーシップや意思決定力などのマネジメント能力を体系的に育成する取り組みです。
キャリア上の不安や昇進への心理的ハードルを乗り越える支援も含まれており、企業としてのDE&I推進にも直結する育成施策といえます。
一般的な管理職育成は、性別を問わない汎用的なスキル習得を目的としています。
それに対し、女性管理職育成では、昇進に対する心理的なハードルやロールモデルの不足、キャリアとライフイベントの両立に対する不安など、女性特有の課題にも寄り添いながら、意欲と自信を高める設計がなされています。
対象者本人の納得感を大切にしながら、実務と結びついた学びを提供する点が特長です。
女性管理職育成プログラムは、女性管理職の登用を通じて組織の多様性を広げるだけでなく、多様な視点を経営に取り入れることで、イノベーション創出や意思決定の質の向上にもつながります。
組織文化の刷新や企業価値向上を促す、戦略的な人材投資といえるでしょう。
女性管理職の育成には、スキルや知識の習得に加え、実践的な経験や内省を通じた成長を促すさまざまな手法が活用されています。
1on1やグループセッションなどのコーチング手法を通じて、参加者自身のリーダーシップスタイルを発見・強化します。内省と対話を重ねながら、組織を動かす力を実践的に磨いていくことが可能です。
人事としても、本人の成長過程を可視化しやすく、上司へのフィードバックにも活用できます。
社内外の女性管理職をロールモデルとし、成功事例や失敗談に触れることで「自分にもできる」という自信を育てます。メンターによる継続的なサポートは、成長意欲の維持にも効果的です。
心理的支援だけでなく、実践知の共有による視野の拡張にもつながります。
女性管理職育成プログラムでは、ライフイベントとキャリアの両立を支援する取り組みが重要です。
将来のライフイベントも見据えたキャリア開発支援を行い、仕事とプライベートの両立を実現する視点を提供します。環境を整えるための社内制度の整備も欠かせません。
制度や支援環境とあわせて、現実的なキャリアデザインを描く支援が求められます。
安心して意見を交わせる環境づくりのために、アサーティブ・コミュニケーションや傾聴の技術を習得します。心理的安全性の高いチームは、個人のパフォーマンス向上だけでなく、組織全体の成果にも良い影響を与えるとされています。
女性管理職育成においては、対話の質を高める支援が重要です。
マツダでは、2025年度までに女性管理職を100人に増やす目標を掲げ、女性活躍を本格的に推進し始めました。しかし、候補者の多くが「管理職になりたくない」と感じており、昇進意欲の低さが大きな障壁に。
背景には「完璧でバリバリ働く」従来型の管理職像や、長時間労働への不安があり、「自分には無理」という思い込みや自信のなさが影響していました。
制度改革は進んでいたものの、運用する人のマインドが変わっていないことも課題でした。
この課題を解決するため、マツダはNOKIOOと連携し、4ヶ月間にわたる女性リーダー育成プログラムを開始しました。研修では「管理職=長時間労働」ではなく、「チームで成果を出す」マネジメントスキルを重視。
受講者は、「マネジメントはセンスでなくスキル」と捉え直し、「私にもできるかもしれない」という小さな自信を得ることができました。
女性管理職の育成は、制度整備だけでなく、納得感ある育成機会と支援環境づくりが不可欠です。
組織に合ったプログラム設計には、専門的な知見を持つ外部パートナーの活用も有効な選択肢のひとつでしょう。
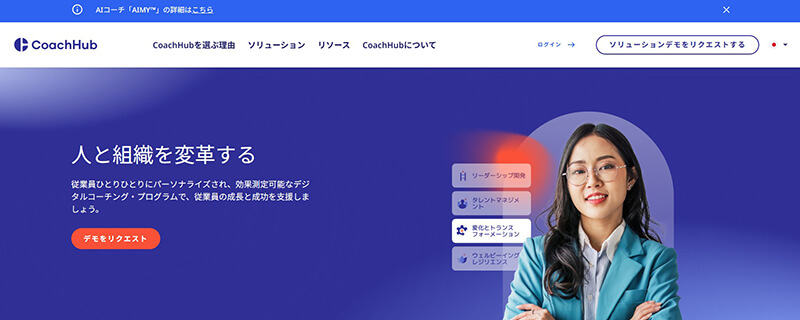
傾聴力・共感力・リーダーシップ力
行動科学・心理学に基づいたアプローチで、企業の管理職やチームリーダーが自身の行動や思考を深く見つめ直すプログラムを展開。
傾聴力・共感力・リーダーシップ力などが育つことで、社員の心理的安全性を高め、チームのエンゲージメントが向上します。

フィードバック力・対話力
実務に即した1on1支援と360度フィードバックなどにより、プレイヤー型の管理職が「人を育てる」マネジメントへ意識を転換。
OKR設計やピアセッションを通じて、対話力やフィードバック力“育成に必要なスキル”を実践の中で磨きます。

自己認識力・ビジョン構築
エゴグラム・360度サーベイ・AI対話分析を活用した1on1で、自己認識力とビジョン構築力を強化。
「どう見られているか」「何を大切にしているか」を問い直し、自らビジョンを語り、導くリーダーへの意識変革を支援します。