こちらの記事では、メンタルコーチングについて解説しています。メンタルコーチングの概要や組織が抱えているメンタル課題、メンタルコーチングを行うことによって期待できる効果をまとめています。
「メンタルコーチング」とは、社員が心の状態を整え、自己理解と行動の改善を通じ、安定した成果を発揮できるように支援するコーチング手法を指します。
コーチングとは、対話を通じて気づきを促してさまざまな目的に導いていくことを指していますが、特に精神的な面に訴えかけていくものがメンタルコーチングです。その中でも、ビジネス分野のメンタルコーチングでは、従業員が自主的に目標を達成するための課題や方法に気づき、より良いパフォーマンスを発揮できるようにコミュニケーションをとっていくことが特徴となっています。
メンタルコーチングと混同しやすいものとして、「メンタルトレーニング」や「カウンセリング」がありますが、メンタルコーチングは「技術を鍛える」のではなく、「心の状態を安定させるための対話」に重点を置いている点がメンタルトレーニングとの違いといえます。また、カウンセリングの場合は対象者の話を聞くことの比重が大きくなりますが、メンタルコーチングはそれよりも能動的なアプローチとなり、相手の強みなどを引き出して目標達成を支援する、といった側面が大きくなります。
組織が抱えることが多いメンタル課題のひとつとして、「社員がストレスや不安を抱えており、パフォーマンスを発揮できない」という点が挙げられます。
職場においては、さまざまな点がストレスの要因となります。例えば、業務の量が多くいつも時間に追われて作業をしている、勤務時間に仕事が終わらずいつも残業が発生し、十分に休息の時間が取れないといった業務の量に関することや、職場の人間関係が悪化している、周りの人とのコミュニケーションがうまく取れないといった人間関係でもストレスが大きくなる可能性もあります。
そのほか、精神的に負担が大きい業務を任されている、仕事の失敗やプレッシャーを感じている、顧客や取引先からのクレームを受けるなど、さまざまな要因でストレスや不安を感じるケースがあります。このような問題を抱えている場合にはその社員が本来持っているパフォーマンスを十分に発揮することができない、という状況に陥る可能性があります。
部下がメンタル面の不調を抱えている場合、管理職はケアを行うことが求められます。しかし、メンタル面の不調は目に見えにくいために対応について戸惑いや難しさを感じてしまい、十分な対応ができないといったケースもあるのではないでしょうか。
例えば、不調について話をされたもののどう対応していいかわからない、ひとりひとりの感じ方に個人差があることから判断が難しい、不調を訴えている部下への仕事の割り振りに悩んでいるなど、管理職もさまざまな面で対応に悩んでいることが多くあります。
また、近年ではリモートワークを取り入れている企業も多くあります。その場合、毎日直接会って接するわけではないことから、部下の不調をうまく把握できないといったケースも考えられます。
メンタルに不調を抱えている場合、休息が必要となるためにやむを得ず休職や離職を選択するケースもあります。回復のためには休職などが必要ではあるものの、この点により組織全体がさまざまな課題を抱える可能性も考えられます。
例えば、休職した社員が担当していた業務を周りの従業員が担当することになった場合には、単純に業務負担が大きくなります。割り振られる業務量によっては、業務時間内に作業を終わらせられず、残業が必要になるといった状況も考えられます。このように業務の負担が他の社員に行くことによって、他の社員もドミノ倒し的にメンタルに不調を抱えてしまう可能性も否定できません。
このように、メンタル不調の増加は組織全体にもさまざまな影響を与える可能性があるために、企業においてもしっかりと対応していくことが大切になります。
コーチングを行う際には、コーチが社員に質問を投げかけていきますが、その過程で社員は自分自身が持つ価値観や考え方に気づき、自己理解を深められます。例えば「どうしてその目標を達成したいのか」「自分が本当にやりたいことは何なのか」という質問に向き合うことによって、本質的な課題が見えてきます。
自己理解が深まると、自分自身が持っている強みや弱みを客観的に認識ができる、迷いや不安を軽減できるため、意思決定がしやすくなるといった点に加えて、自分自身に合ったキャリアやライフスタイルを選択しやすくなるといった面もあります。
メンタルコーチングでは、ストレスマネジメントや感情のコントロールについてサポートを行っていきます。
そのため、従業員はメンタルコーチングを受けることによって、自身のメンタルヘルスの保ち方が理解できるようになり、ストレスを感じた場合にも自身で課題解決を行いやすくなるといった面もあります。
メンタルコーチングを行うことで、社員のメンタルヘルスの安定につなげられれば、職場の生産性向上や離職率の低下につながっていくことも期待できます。
ただし、中にはメンタルコーチングのみでは解決できない問題もあるため、そのようなケースについては他の方法を検討することになります。
メンタルが不調な状態に陥ってしまうと集中力が持続できなくなることから、作業効率が低下するという傾向が見られます。また、集中力が続かないと作業ミスや遅れが目立つようになり、これまでできていた業務ができなくなってしまう、という状況になることもあります。
どのような場面でパフォーマンスが低下するのか、どのような場面でミスが発生するのかといった自分の特徴を振り返ることによって、パフォーマンスの向上を目指すことができるようになります。
メンタルコーチングの実践によって、社員の自己効力感やレジリエンスの向上が期待できます。
「自己効力感」とは、「自分は目標を達成するための能力を持っている」と認識することを指しています。簡単にいうと、「自分ならできる」「きっとうまくいく」と思える認知状態です。
さらに、小さな成功体験をいくつも積み重ねて自信を育てていくことによって、レジリエンスの向上に繋げられます。「レジリエンス」とは困難な状況やストレスに対処し、回復する能力を指しており、向上することによって、プレッシャーやミスなどにも動揺せずに対応できるようになります。現代社会は変化が激しく予測困難な時代においては、さまざまなことを乗り越えていくためにもレジリエンスの強化に取り組むことも大切であるといえます。
メンタルコーチングを取り入れることによって、業務への集中力を高められ、パフォーマンスの改善につながると考えられます。
これは、メンタルコーチングは、コーチとの対話を通じて「自分が何を大切にしたいのか」「達成したいことは何か」という点が明らかになり目標を達成する力を高められるため。社員それぞれが目標を達成する力を向上できれば、企業全体のパフォーマンスも高まっていくことが期待できます。
「エンゲージメント」とは、「婚約、誓約、約束、契約」を表す言葉ですが、ここから「個人と組織の成長の方向性が連動しており、互いに貢献し合える関係」という意味でも使われています。
エンゲージメントが高い組織の場合、ひとりひとりの従業員が企業や組織を信頼し、自身だけではなく企業の成長に向けて意欲的に取り組めます。このようにエンゲージメントが向上することによって、組織力の高まりや業績向上が期待できるとともに、離職率が低下する可能性もあります。
ビジネスコーチング以外の法人
向けの
コーチングの種類
について詳しく見る
こちらの記事では、メンタルコーチングの概要や期待できる効果について紹介してきました。
メンタルコーチングは、社員の心の安定と成長を支援することによって、組織全体の活力を高めていくアプローチです。コーチングにより、自己理解を深める・感情のコントロールができるようになるといった効果が期待でき、安定したパフォーマンスを発揮できるようになります。
企業が人材の定着や育成を考える上でも、この方法は注目度の高い支援手段といえます。社員のメンタルヘルスケアに取り組みたいと考えている場合には、このメンタルコーチングの実施も検討してみてはいかがでしょうか。
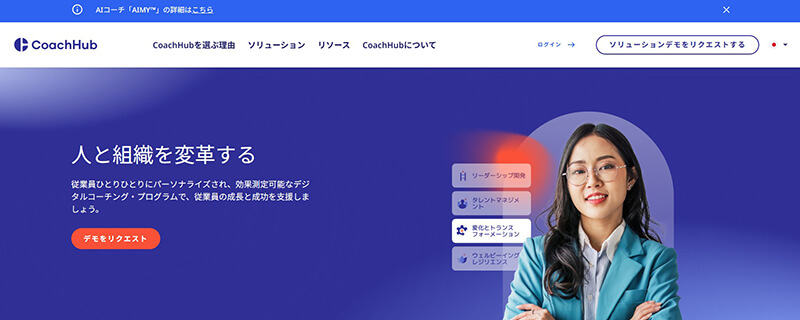
傾聴力・共感力・リーダーシップ力
行動科学・心理学に基づいたアプローチで、企業の管理職やチームリーダーが自身の行動や思考を深く見つめ直すプログラムを展開。
傾聴力・共感力・リーダーシップ力などが育つことで、社員の心理的安全性を高め、チームのエンゲージメントが向上します。

フィードバック力・対話力
実務に即した1on1支援と360度フィードバックなどにより、プレイヤー型の管理職が「人を育てる」マネジメントへ意識を転換。
OKR設計やピアセッションを通じて、対話力やフィードバック力“育成に必要なスキル”を実践の中で磨きます。

自己認識力・ビジョン構築
エゴグラム・360度サーベイ・AI対話分析を活用した1on1で、自己認識力とビジョン構築力を強化。
「どう見られているか」「何を大切にしているか」を問い直し、自らビジョンを語り、導くリーダーへの意識変革を支援します。