こちらの記事では、「コーチング型マネジメントプログラム」について解説を行っています。どのようなマネジメント手法なのかという点や、取り入れた際に期待できる効果などをまとめました。組織のマネジメントについて情報を集めている方などはぜひ参考にしてみてください。
「コーチング型マネジメント」とは、従来のような指示・監督型マネジメントとは異なっているものです。コーチング技術を活用したものであり、部下の自発性や強みを引き出すことを目的としたマネジメント手法です。
ポイントは、「傾聴」「質問」「承認」「フィードバック」を通じ、部下自身が考え、行動する力を育む点。例えば業務を遂行する中で、何か問題やトラブルが発生した際、壁にぶつかった際などにも周囲に頼りすぎるのではなく、自らが考え、自主的に問題の解決に繋げられるようなスキルを獲得することを目的としています。
このように、自分で考え・行動に移せるスキルが身につくと、個人が持っている強みや個性を活かせるようになる点に加えて、モチベーションの向上につながるという効果も期待できます。さらに、個人個人が自主的に動けるようになると、組織全体のモチベーションの向上や業務効率化につながっていくため、非常に注目されているマネジメント方法であるとされています。
企業の中では、「指示待ち」の風土が根付いてしまい、上司からの具体的な指示やマニュアルがないと仕事ができない、自ら判断した上で行動するという点に対して消極的であることが課題となっている組織もあります。このような風土が根付いてしまうと、主体性が育ちにくく業務の効率が低下する可能性が考えられます。
指示待ちの状況を生んでしまう原因として、その組織に「上司の指示を待つべき」という文化がある、部下自身の経験不足やスキル不足により自信を持って動けない、失敗を避けたいという思いから指示を待ってしまうといったものが挙げられます。そして、上司が細かく指示を出しすぎており、部下が判断する必要がない状況を作り出しているといったことも考えられます。
人材育成は長期的な視野が必要になりますが、企業によっては短期的な成果に偏ってしまっており、育成が後回しになってしまうケースがあります。
多くの場合、育成担当者は通常業務と並行しながら育成のための指導を行っていきます。しかし、日々の業務に追われてしまった場合には、人材育成の優先度が下がってしまうことも。このような状況で育成が後回しになっていると、学ぶ側のモチベーションも低下してしまうといった面もあります。
上司のスキル不足も課題としてあげられる場合もあります。必要とされるスキルはさまざまなものがありますが、マネジメントを行う上で求められる「傾聴スキル」や「質問スキル」が不足していると、1on1を行ったとしても形式的な内容となってしまい、せっかく機会を設けても部下の成長に繋げられない、という状況に陥ってしまいます。
コーチング型マネジメントには、「傾聴」「質問」「承認」「フィードバック」といったスキルが必要になりますが、コーチング型マネジメントプログラムによってこのようなスキルを体系的に習得可能です。さまざまなスキルを身につけることによって、単なる指示や命令のみを行うのではなく、部下の話に耳を傾けて意見を引き出しつつ、効果的なマネジメントを行えるようになります。
コーチング型マネジメントプログラムによって部下の強みを引き出すことができ、それぞれの個性を活かすマネジメントを実践できるようになります。
例えば、コーチング型マネジメントの中ではフィードバックを行っていきますが、これは相手の行動や成果を評価し、成長を支援するためのもの。ひとりひとりに合わせたフィードバックを提供すると、部下は自分の強みや改善点について理解しやすくなります。
さらに、ポジティブな評価と改善点の双方をバランスよく提供していくことで、部下自身が受け入れやすいフィードバックを行えるようになります。このプロセスにより部下の能力を伸ばし、目標達成に向けた行動を促せるようになります。以上のように個性を活かすマネジメントを提供することによって、部下の成長をサポートできます。
質問や対話を通じて行われるコーチング型マネジメントでは、活発なコミュニケーションが促されます。そのため、チーム内でもお互いの強みや個性の理解や尊重にもつながり、信頼関係が強化されるといった面もあります。このことによってより強いチームワークが形成されます。
さらに、チームメンバーの得意な部分などの理解を深められますので、業務の分担や協力体制の分担も効果的に行え、チーム全体のパフォーマンス向上や持続的な成長にも繋げられます。
コーチング型マネジメントの実践により、部下の自主性やモチベーションが高まるといった効果が期待できます。
このマネジメント方法は、指示を待って行動するといった従来型のマネジメントとは異なり、部下が自ら考えて行動するという自主性を育てることを目的としているもの。業務の進め方はもちろん、もし問題が発生した場合の解決方法などについても自ら考えて行動していけるようになります。
部下自身が自ら考えて行動して問題を解決できた場合、その経験は部下の大きな自信になりますし、自身の成長を感じられるきっかけにもなります。自身の成長が実感できる環境や自分の努力が評価される、自分の行動がチームの成果につながったことを感じられるといった環境は、やりがいを感じやすくなるといったメリットもあります。
そのため定期的なフィードバックを行い、部下自身が進捗を確認できる機会を提供することが重要となります。目標達成を目指す中で受けた評価はさらなる原動力になりますし、上司からの評価によって自分の努力が組織の成功につながっていると感じられると、業務に対して「これからも頑張ろう」「より良い仕事をしよう」といったモチベーションの向上にもつながっていきます。
コーチング型のマネジメントを行うに当たっては、上司と部下が対話を行い、部下が持つ強みや得意分野、不得意分野などについて細かく把握した上で、それぞれに合ったマネジメントを行っていきます。
それぞれのメンバーに寄り添いながらマネジメントを行っていくことにより、ひとりひとりの長所を伸ばしたり潜在的な可能性の発見につながったりするケースもありますし、苦手な分野の克服や短所の改善を行うことも可能です。
このように、個人の能力開発や成長支援を進めていくことによって、次世代のリーダー育成に繋げられるというメリットもあります。
組織の中でコミュニケーションが活発化すると、お互いへの理解が深まります。相互理解の深まりは、職場全体の信頼関係構築にもつながり、活発な意見交換がしやすい雰囲気を作れます。
組織に所属する誰もが不安を感じずに意見を述べられる、心理的安全性が確立された環境では、新しい発想やさまざまなアイデアが生まれやすくなり、市場の変化などにも迅速に対応することが可能に。さらに課題の共有などもしやすくなり、問題が発生した場合でもスピーディーな対応ができるようになります。目標に向かってチーム全体が一体感を持って取り組めるようになることから連携が強化され、効率性と成果が向上するといった効果も期待できます。
こちらの記事では、コーチング型マネジメントプログラムについて解説を行ってきました。
コーチング型マネジメントとは、部下の主体性を育て、持続的な成長を可能にすることを目的としたアプローチです。従来行われてきたような指示命令型とは異なり、「傾聴」や「質問」を通じて部下の長期的なモチベーションの維持と成長を促せるようになります。さらに、上司と部下の間でのコミュニケーションが活発になり、お互いの理解を深められることからチーム全体の信頼関係強化にもつながり、業務を効率的に進められるようになるといったメリットもあります。
このような面から、コーチング型マネジメントプログラムを取り入れることは、自主性を重視するマネジメント文化の浸透に役立てられるため、ぜひチェックしておきたいアプローチであるといえます。
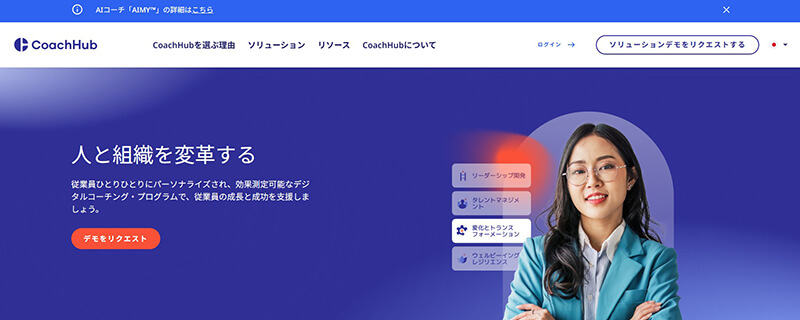
傾聴力・共感力・リーダーシップ力
行動科学・心理学に基づいたアプローチで、企業の管理職やチームリーダーが自身の行動や思考を深く見つめ直すプログラムを展開。
傾聴力・共感力・リーダーシップ力などが育つことで、社員の心理的安全性を高め、チームのエンゲージメントが向上します。

フィードバック力・対話力
実務に即した1on1支援と360度フィードバックなどにより、プレイヤー型の管理職が「人を育てる」マネジメントへ意識を転換。
OKR設計やピアセッションを通じて、対話力やフィードバック力“育成に必要なスキル”を実践の中で磨きます。

自己認識力・ビジョン構築
エゴグラム・360度サーベイ・AI対話分析を活用した1on1で、自己認識力とビジョン構築力を強化。
「どう見られているか」「何を大切にしているか」を問い直し、自らビジョンを語り、導くリーダーへの意識変革を支援します。